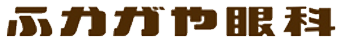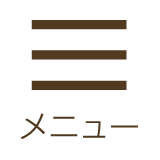白内障の手術は進行してからの方がいいでしょうか?
2011年7月25日(月)
白内障手術は、この20年で大きく進化しました。嚢内法から嚢外法へ、そして超音波を使用した手術へと進化しました。嚢内法とは、大きな傷口から、水晶体をそのカプセルとともに丸ごと摘出し、数針縫合します。眼内レンズは挿入することができず、手術後にコンタクトレンズが必要でした。嚢外法とは、大きな傷口から、水晶体のカプセルを残してそれ以外を丸ごと摘出し、カプセル内に眼内レンズを挿入して、数針縫合します。いずれも麻酔は球後麻酔(目の下に注射をします)で、入院も当たり前でした。
このような方法であったのに対し、現在の標準的な手術方法は、3ミリ以下の傷口から、水晶体をカプセルを残してそれ以外を超音波で破砕・吸引し、カプセル内に小さく折り畳んだ眼内レンズを挿入し、縫合もしません。目薬の麻酔のみで、10分少々で終わり、日帰りで可能な手術です。このような手術方法も、器械や器具、眼内レンズの進歩のおかげなのです。
当然これらの方法で手術後の経過は異なります。かつて嚢内法や嚢外法が主流だった頃、現在の方法よりもはるかに手術中や手術後の合併症も多く、手術後回復に時間がかかり、手術後の見え方の質も今ほど良くなかったため、白内障が相当進行してからしか手術は行いませんでした。技術が進歩した現在では、少し早めに手術を行っても、手術後早期から良好な見え方が期待出来るようになりました。その結果、ここ数年の日本の白内障手術件数は毎年約100万件で、最もありふれた手術となりました。
しかし、相当進行した白内障の手術は、現在の手術方法では困難で、やはり嚢外法が必要となる場合があります。もう少し早めに手術をしておけばすぐによく見えるようになったのに、放っておいたために手術時間も長くなり、回復にも時間がかかってしまった・・・このようなことにならないよう、適切な時期に手術をされるのがいいと思います。
白内障はまた手術できるのですか?
2011年7月20日(水)
白内障手術は、濁った水晶体(レンズ)を取り除き、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。基本的に手術は一度しか出来ません。もう一度手術を行わなければならないのは、術中合併症により眼内レンズを入れることが出来なかった場合、術後眼内レンズが眼内に落下した場合、眼内レンズの予想屈折度が大きくずれた場合(近視を予定して遠視となった場合など)、眼内レンズが濁った場合など特殊な場合に限られます。これらはいずれも術前に必ずしも予想や予防出来るとは限らず、手術の失敗とはいえない場合も多々あります。
術後しばらくの間はよく見えていたのに、その後徐々に視力が低下してきたとすると、後発白内障であるか、眼底(視神経・網膜)に異常がある場合が考えられます。後発白内障の場合は、先にお話した通りレーザーで治療出来ます。眼底の異常の場合は、治療を行っても視力は回復しない場合もあります。
年齢とともに眼底疾患の頻度も増加します。緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症などが代表的です。眼底疾患では白内障手術でレンズを交換するように、視神経や網膜を交換するような手術は出来ません。病気の進行を遅らせたり、勢いを落ち着かせるのが治療の目的となります。これらの病気の早期発見のためにも、白内障手術後しばらく経過した後にも、定期的に検査を受けられるのがいいでしょう。